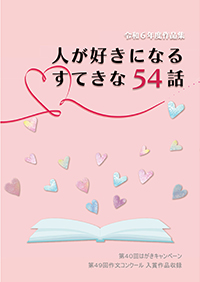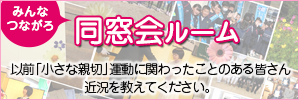山口県 下松小学校 4年 守政 拓哉
ぼくは、下松市の所田(ところだ)というところに住んでいます。その所田地区の清そうボランティアが5月にありました。去年は、コロナウイルスのえいきょうで、じっしされませんでしたが、ぼくはじっしされるときは、毎年、母とさんかしています。
今年も所田地区の人たちいっしょにじょ草作業をする中で、近所の人たちとたくさん話をしました。「今、小学校は何年生なの。」「小学校は楽しいの。」
などと聞かれながら、草をぬいたり、ごみを拾ったりした活動は楽しかったです。そんな中で、一人の女の人の言葉が、とてもいんしょうにのこりました。
「今日の清そう活動でとてもきれいになったけれど、ごみがこれだけ集まったということは、だれかが、こんなにごみをすてているということね。」
その言葉を聞いて、ぼくも本当にそうだなと思いました。毎日、このあたりを歩いて小学校に通っていますが、この清そう活動にさんかして、はじめてごみの多さに気がつきました。ごみをすてるのも「だれか」であり、それを拾ってくれるのも「だれか」だと思いました。その拾ってくれる「だれか」にぼくたちは感しゃをし、その拾ってくれる「だれか」にぼくたちもならなくてはならないと今、思っています。
この夏休み、ぼくはときどき、父と散歩をしています。この前の土曜日の朝も、父と下松小学校のまわりをいっしょに歩きました。すると、小学校の正門の前で、一人の男の人がもくもくと草をぬいていました。その男の人のそばには、草でいっぱいになった白いごみぶくろが二つありました。
この人も、ごみを拾ってくれている「だれか」の一人だと思います。父の話によると、この男の人はいつも朝早くから、小学校のまわりのごみを取ったり、草をぬいたりされているそうです。
この男の人のように、地いきのために何かができる「だれか」になるためには、どうしたらいいのでしょうか。そして、それを続けていくためには、何が大切なのでしょうか。
これらのことについての正しい答えは、ないのかもしれません。しかし、ぼくが考える答えは、まず「自分の身のまわりで、自分ができることから始めてみる」ということです。
ぼくは今、一週間に一度、家の洗面所のそうじを手伝いとしてがんばっています。かかる時間は、15分ぐらいで、それほど大変ではありません。これは、自分の家の手伝いでむずかしいことではありませんが、こうしたことを続けていく習かんが身につけば、しょう来、地いきのために何かをすることができる「だれか」になれるのではないでしょうか。
よい習かんを続けていくときには、まわりの人からの声も大切です。洗面所のそうじのあとに、母から、「きれいになったね。どうもありがとう。」と言ってもらえると次もがんばろうと思います。
この気持ちをわすれず、「自分のできること」から始め、地いきのために何かができる「だれか」にしょう来なりたいです。